
節分は幼いころから豆まきを学校や自宅で行うなど生活に密着した季節の行事です。豆まきをして鬼を退治し、福を招き入れた後に豆を食べてこれからの1年の健康を願いますが、豆を食べるときにいくつ食べるのかご存じでしょうか。今回は節分に関する豆知識や食べる豆の数のかなどを紹介していきます。
節分
節分とは
節分は季節行事の一つで、各季節の始まりである立春・立夏・立秋・立冬の前日に行われます。また、節分は「季節を分ける」ことも意味しているといわれています。
季節の変わり目には邪気(鬼)が生じると信じられており、それを追い払うための悪霊払いが執り行われていたことが由来です。その方法が庶民に広まり、豆まきをする、ヒイラギの枝にイワシの頭を刺したものを玄関口に立てておくなどの方法で邪気を払うようになったと言われています。 節分では欠かせない「豆」ですが、なぜ豆をまいたり食べるようになったのでしょうか。 なぜ豆? このような意味で鬼に豆をぶつけ、邪気を払い無病息災を願うようになりました。 福豆で邪気退治 節分では「福豆」が正式な豆です。福豆とは炒った大豆を神棚にお供えしたもの、または神社やお寺でお祓いをして清めた豆のことです。最近では神社やお寺で豆のお祓いをすることは減り、自宅の神棚にお供えする、または目線の高い場所に白い紙を敷いてお供えしても良いとされています。 豆まき 豆まきは、季節の変わり目に来る邪気(鬼)を追い払うものです。豆まきの方法は、地域や家庭によっても異なりますが、一般的に夜行われます。夜は邪気が活動を始める時間帯だからです。 豆知識 さまざまな豆まきの方法 このように豆まきといってもさまざまな方法があります。 共通するのは、 ということです。 年男・年女はその年の干支に生まれているので縁起が良く、厄年の人は豆まきを厄払いとして行うことができるためです。 豆はいくつ食べればよい? 豆まきが終わると、炒った豆を食べることが習慣です。豆を食べることで、体に福を取り込み、一年健康に過ごせますようにという願いが込められています。 食べる豆の数は というのがならわしです。 数え年は、生まれたその日にすでに1歳で、元旦に歳を取るという考え方です。例えば、2020年4月に生まれた人はその時点で1歳とされ、2021年の1月1日に歳を取り、2歳になるという数え方です。 数え年で食べる場合は、自分の年齢にプラス1粒します。「プラス1粒=来年」ということを意味します。つまり、来年も健康に過ごせますようにという意味で多めに食べることになったと言われています。 食べきれない場合は? 年齢を重ねるごとに、食べる豆の数も増えるので「こんなにたくさん食べきれない」という場合もあると思います。 そのような時におすすめなのが「福茶」です。 福茶は、福豆を入れた縁起の良いお茶です。炒った豆3粒にお湯を注ぐだけで出来上がりです。 さらに、梅干し1個、昆布の佃煮か塩昆布を入れると運気がアップするといわれています。 関西を中心に、江戸時代末期ごろに流行っていた恵方巻。節分の夜に、その年の恵方を向いて7種の具が入った寿司巻きを無言でまるかじりします。商売繁盛や無病息災を願ったものです。現在では恵方巻はコンビニやスーパーで手軽に買うことができます。 2021年の恵方は「南南東やや南」です。 節分には、邪気を払い、福豆を食べることでこれから1年の無病息災を願うという意味があります。現在では大豆ではなく落花生をまく家庭もあるようです。落花生は殻に入っているため、誤飲などの確率も低く小さいお子さんがいても安心ですね。 今年の節分は、これからの幸せを健康を願い豆まきを行ってみてはいかがでしょうか。 
なぜ節分で豆を使うのか
豆まきの習慣


福茶とは

恵方巻とは

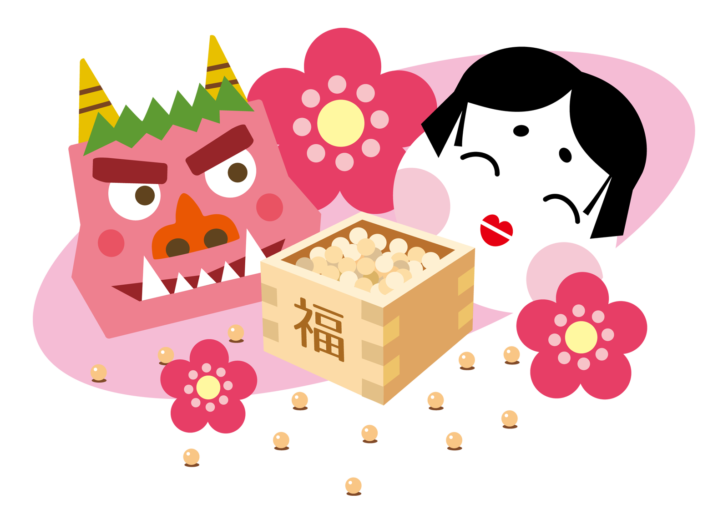
まとめ